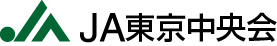東京農業歴史めぐり
砂川ゴボウ
江戸時代から昭和にかけての江戸・東京のゴボウは、東の「滝野川ゴボウ」に対し、「砂川ゴボウ」は西の代表でした。
砂川ゴボウの起源については明らかではありませんが、立川市史によると元禄年間(1688〜1704)、砂川村が開墾された頃、農民があたりに生えていた野生のゴボウを掘って食べたのがきっかけで、しだいに栽培されるようになりました。
その後、諸国の大名が、江戸参勤交代の際に砂川ゴボウの種子を持ち帰って領内に栽培させたので、砂川ゴボウの名は各地に広まり有名になりました。しかし、砂川村でのゴボウの栽培が最もさかんになったのは明治初年以降のことで、明治25年頃からは三鷹村や小金井村方面に広まり、その後はさらに小平、東村山、保谷、武蔵野の各町村に拡大し、関東ローム層という良質のの土壌から高品質のゴボウが生産されていました。