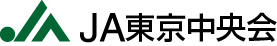東京農業歴史めぐり
関野クリ
江戸時代、江戸近郊には年貢米のほか、将軍家が消費する新鮮な野菜、果物、魚介類などの上納を指示された村がありました。多摩地域では多摩川の鮎、府中の真桑瓜、そして、小金井のクリもその一つでした。
武蔵野新田の世話役、川崎平右衛門が、延享4年(1747)に、小金井村に3,600坪に及ぶ幕府の御料林「十ケ新田栗林」(現在の新小金井駅西側一帯)を設けてからは、クリは小金井の名物となりました。
安政(1854〜59)の頃まで活躍していた当神社の氏子、植木屋の庭田五郎兵衛は「八王子付近の山クリを拾って、自宅の畑にまいたものから育成した」(子孫の丈俊氏談)クリに「五郎兵衛」と名付けたが、その優秀性が認められ、地元で広く栽培されていました。
その後、いつとはなく土地の名を取って「関野クリ」と呼ばれるようになりました。しかし、クリの害虫、クリタマバチに弱かったため、その後減少の一途をたどりました。