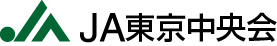東京農業歴史めぐり
吉祥寺ウド
武蔵野八幡宮周辺は旧武州多摩郡吉祥寺村として、江戸時代より畑作農業が盛んな所でした。五日市街道に面していたので、江戸との交流も多く、野菜や薪の供給地でもありました。
ウドは数少ないわが国原産の野菜の一つで、古代から自生のものが利用されていました。記録によれば、この地で栽培されるようになったのは、江戸時代後期の天保年間(1830〜44)とされています。
元来強健で適応性の広いウドは、武蔵野にもよく適し、特に冬から春にかけては野菜が不足していたことから、この時期に生産されたウドは独特の歯ざわりと香りで、江戸庶民に歓迎されました。
明治、大正、昭和と栽培は益々盛んになり、吉祥寺ウドとして広く知られました。しかし、その陰には篤農家による創意と努力により、他に例を見ない純白に育てる、「穴蔵軟化法」等、技術開発のたゆまぬ研究がありました。都市化により栽培面積は減少してきましたが、特産吉祥寺ウドの名声は全国に知られるようになりました。