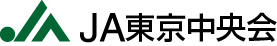東京農業歴史めぐり
東京のナシ栽培の起源
武州多摩郡長沼村(現在の稲城市東長沼)の当青渭神社周辺は、古くから有名なナシ産地として知られています。その起源は古く元禄年間(1688〜1704)、当時の代官増岡平右衛門と川島佐次右衛門が、山城國(京都)に旅行した折りに、淡雪(アワユキ)という品種の苗木を持ち帰って植えたのが、始まりとされています。
その原木は明治22年まで、東長沼の川島邸内に保存されていました。ひじょうに大きなもので、幹の周囲が180センチ余り、棚作りにされていて枝の広がりは、100平方メートルにも達していたと言われていました。
江戸時代、東葛西の新川(江戸川区)沿には新川ナシの産地がありました。また、明治初期に荏原郡六郷村羽田(現在の羽田空港付近)や、橘樹郡大師河原村(現在の川崎市川崎区)にも大産地がありました。