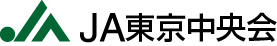東京農業歴史めぐり
高井戸節成キュウリ
旧豊多摩郡高井戸村(現在の杉並区上高井戸・下高井戸)付近は、江戸時代に開拓されました。甲州街道に面し江戸にも近く、古くから野菜の産地でした。
キュウリは明治になってから大量に消費されるようになりましたが、高井戸キュウリは「節成り」といって、親づるの節ごとに雌花をつける性質があり、栽培がしやすい品種で、明治の中頃から昭和の中頃まで、この地を中心に高井戸節成キュウリと呼ばれ、広く栽培されていました。
南に隣接する旧荏原郡馬込周辺(現在の大田区東馬込・西馬込)では、節成りで果実の下半分が白い、馬込半白節成キュウリが栽培され、北に隣接する旧北豊島郡(現在の練馬区)では、親づるには雌花をあまりつけず、子づるに雌花をつける豊島枝成キュウリが栽培されていて、その合流地であったこの地で両者の長所を持ったキュウリが育成されました。
この特産地も、都市化や、ハウスなどの施設栽培の普及、消費者ニーズの変化などにより、東京農業の歴史に名を止めるだけになってしまいました。